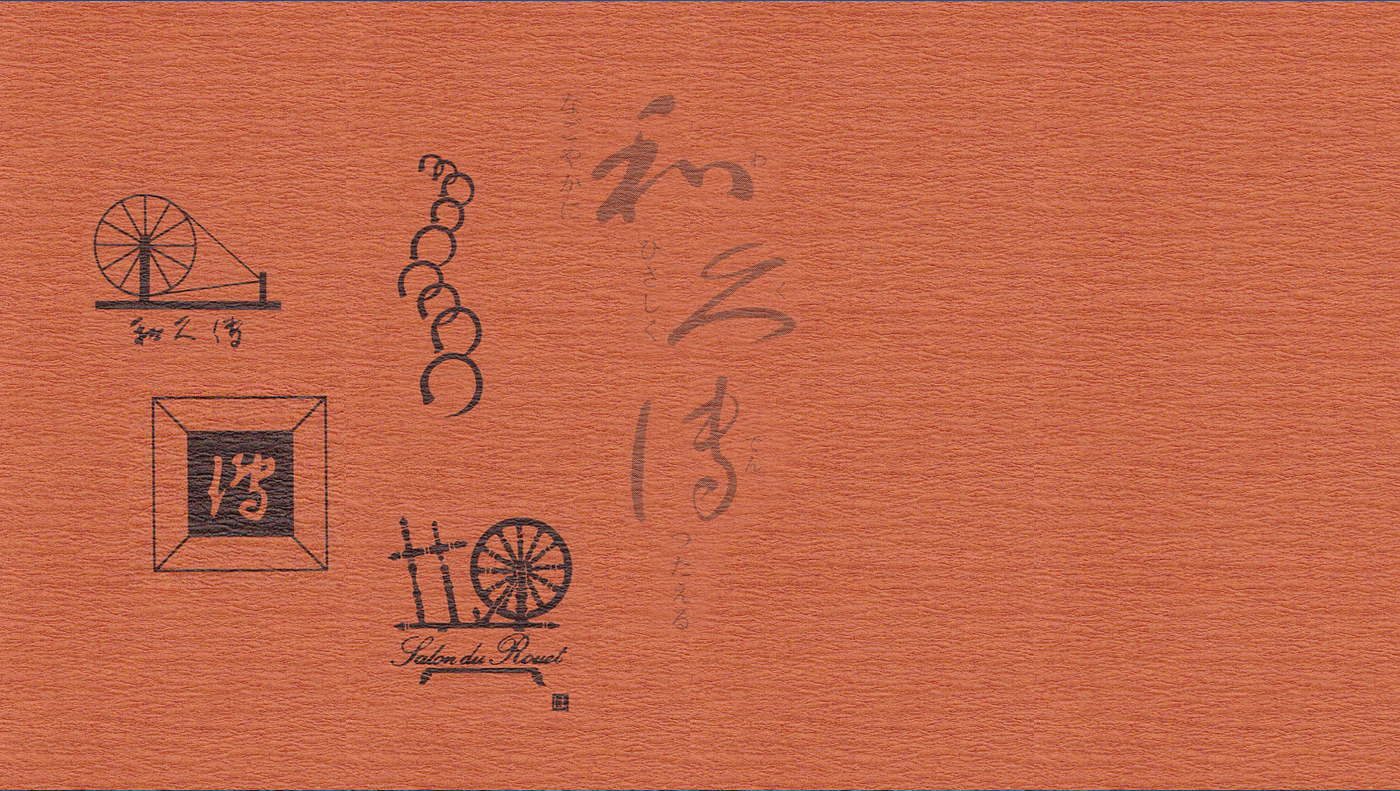和久傳の歴史
|
ふるさと
和久傳のふるさとは京都府の北部、京丹後。日本海をのぞむのどかな里山です。日本書紀にも記されるほど歴史は古く、江戸時代以降は、日本最大の絹織物「丹後ちりめん」の産地として栄えました。
和久屋傳右ヱ門
創業は明治3年、初代の和久屋傳右ヱ門が興した旅館にさかのぼります。和久屋はもともと若狭の廻船問屋でした。峰山藩にお仕えするため丹後にうつり、交易地として賑わう彼の地で、当時まだ珍しかった木造三階建の宿を建てました。
こころざし
屋号の「和久傳」は、和久屋傳右ヱ門と妻、久の名にちなみます。和やかに、久しく、傳(伝)える。地域の活力となる商売こそ、和久傳の変わらぬ志。昭和二年の丹後大震災で全壊したおりにも、四年の歳月をかけて再建し、町の復興とともに歩みました。創業から約百年をへて、山麓の約三千坪の敷地にかまえた料理旅館は、七室のみの風雅な造りで、丹後を盛りたてたと伝え聞きます。
ハイカラ
再建を主導した二代目は、自ら木造三階建ての旅館を設計し、自家発電の電灯設備や電気冷蔵庫を導入するなど、常に挑戦ありきのハイカラなひとでした。当時、京都から料理人を迎えるのは一大決心でしたが、新鮮な間人(たいざ)蟹を座敷の囲炉裏端であぶる野趣溢れるもてなしに、京らしい洗練を加えた料理旅館には、食に通じたお客様も方々から訪れてくださいました。
名工との出逢い
京丹後から東山麓の高台寺に移転し、「料亭」和久傳が誕生したのは、昭和57年のこと。ちりめん産業が元気をなくし、京丹後での進退をかけて活路を求めていた和久傳は、名工 中村外二氏が建てた数寄屋建築と出会います。元は尾上流家元の住まい、隅々まで行き届いた名工の普請に後押しされるかのように、都での再出発を決めました。こうして生まれた「高台寺 和久傳」から、次なる章を開いたのです。
間人蟹
和久傳の冬を代表する味、間人蟹(たいざがに)。間人蟹と呼ばれるのは、近場の漁域で、わずかの5隻の小さな底引き網船が水揚げしたずわい蟹だけです。漁は天候の良し悪しに左右されるため、水揚げ量が極めて少ないことで知られますが、セリでは身の詰まりや足落ちに応じて、約50段階に振り分けるほどの徹底した等級づけが行われています。いまもむかしも日帰り漁で、間人港からはわずか5隻の小型船が出港します。シケの多い漁場でもあり、水揚げは決して多くはありませんが、どんな状況であれ、和久傳では上蟹だけを扱います。
コシヒカリ、イセヒカリ
和久傳では、料理につかった蟹殻をまいた肥沃な田んぼで、全店で一年間につかうお米を自分たちで育てています。毎年5月にコシヒカリ、伊勢神宮の神田でうまれたイセヒカリの苗を手植えし、9月は手刈りで収穫するのです。ふるさとにご恩を返したいと、久美浜町の農家に手ほどきを受けつつ、平成17 年から農薬や化学肥料に頼らない昔ながらの農業がはじまりました。2015年からはイセヒカリをつかった生酛仕込みの酒づくりにも挑戦しています。